 せシうだ
せシうだ(記事を読み始める前にこちらをどうぞ)
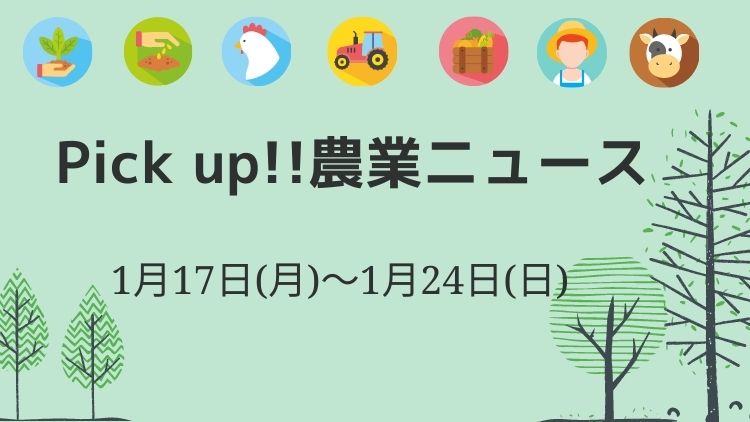
1月17日(日)〜1月24日(日)の期間に日本農業新聞の公式Webサイトに掲載されたニュースです。
こういった方に向けて、私が「重要だ」「面白い!」と思った記事のみをピックアップして紹介してきます。1日1〜2記事、1週間で6〜10記事です。
重要だと判断した部分を引用しつつ、少し分かりにくいところは内容に影響がない範囲で私が書き直しています。タイトルはそのまま引用しているので難しく感じるかもしれませんが、内容は簡潔にまとめているので気軽に読めるかと思います。
一番上が最新の記事で、ページを読み進めていくと時系列的には遡っていくことになります。
小麦、トウモロコシ、大豆の国際相場が値上がりしています。
予想以上に少ない米国の在庫、中国の盛んな買い付け、一部の輸出国による輸出規制の動きなどが相場を押し上げている模様。業界関係者によると長期化する可能性もあるとのことです。
相場上昇の背景には中国のトウモロコシと大豆の活発な輸入があり、疾病で頭数が落ち込んだ肉豚の生産増強が続いているため、飼料需要が急増したといわれています。
小麦は世界で史上最高の生産量になり、消費量も増えるものの、期末在庫量が史上最高の多さになる見通しでした。ところが、年末になって世界最大の輸出国であるロシアが、突然小麦輸出に関税をかけると発表し波紋を広がっています。その後、アルゼンチンやウクライナもトウモロコシや小麦の輸出を規制しました。こうした国々では、自国通貨の下落で国内でインフレ懸念が高まったことから、輸出規制を導入して国内消費者を優先する方針を打ち出しています。
現在生育中の南米の大豆やトウモロコシは、干ばつの影響で生育が遅れている。北半球で進む品薄を解消するのは厳しく、日本国内の商社関係者の間では「当面需給が緩和する要素は見当たらない」という見方が濃厚です。
2021年01月24日
愛知県立大学と愛知県農業総合試験場は、複数の牛の鳴き声のデータを分析し、どの牛が鳴いているか特定することに成功しました。成牛と育成牛の鳴き声を混ぜた状態でも90%以上の精度で識別できたといいます。
人が子どもから大人にかけて声が変わるのは牛も同じです。識別の結果、声帯の筋肉の付き方が成牛と育成牛で違い、牛も人と同じく成長に伴って声道が伸びることを確認し、成牛は声の高さや低さを表す基本周波数の値が育成牛より大きいことも確かめました。
同試験場は「牛がどういう欲求を表現しているか分かるようになれば、病気の兆候や発情の早期発見にも役立つだろう」と期待します。
2021年01月23日
奈良県明日香村は、観光業を営むために村に移住した人などを対象に、耕作放棄地を活用して農業に取り組んでもらうプロジェクトを2021年度から本格的に始めます。
これは、
といった現状を受けて打ち出された策です。
初心者でもできるように、耕作放棄地を整備して貸し出し、作業も手厚く支援します。
明日香村産業づくり課は「中山間地域で農業だけの収入で生計を立てるのは難しいが、観光業と組み合わせて半農半Xで取り組む新規就農者などを増やすことで、耕作放棄地解消の一手としたい」と話しています。
2021年01月23日

2021年01月21日
農水省が全国の養鶏場などを対象に行った飼養衛生管理基準の自主点検で、報告があった農場などのうち、1割ほどに不備があることが分かりました。同省は高病原性鳥インフルエンザが過去最大に広がる中、全農場で管理基準が順守されるよう、指導を続けます。
報告内容によると、「衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用」「家禽(かきん)舎ごとの専用の靴の設置と使用」がともに順守率89%で低い一方、「野生動物の侵入防止ネットなどの設置、点検、修繕」など同95%で高くなっていました。
同省によると、前回の点検で不備があった農場の多くは改善しているため、今回不備があった農場についても防鳥ネットや消毒機器の整備などへの支援の活用を促し、順守率100%を目指す方針です。
2021年01月20日
菅義偉首相が18日の施政方針演説で、日本酒や焼酎について国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産への登録を目指すと表明しました。

政府は日本酒や焼酎について、こうじを使った伝統的な醸造技術として申請する方向で検討しています。ただ、ユネスコは同遺産の登録が無い国の審査を優先しているため、登録件数が多い日本の申請は、実質2年に1回の頻度で審査しており、登録は早くても24年になる予定です。
政府は同遺産の登録を通じて「現場のモチベーションを高めると同時に、日本酒と焼酎の海外での認知度が向上し、国内の需要創出や輸出拡大につながってほしい」(国税庁)と期待します。
2021年01月19日

外国人の新在留資格「特定技能」の農業分野で認められた「派遣」が広がっています。
受け入れ側(農家)のメリットとしては
などがあり、これまで外国人を入れてこなかった家族経営でも受け入れが広がることが期待できます。
負担が減ったことで派遣の受け入れが進めば、外国人にとってもさまざまな農家で働くなど、より豊かな経験を積むことができるようになります。
2021年01月19日
コロナ禍を契機に海外で市民農園が注目されています。
物流が混乱しても自給自足をすれば食材調達が可能だからです。
オーストラリアでは政府支援が加わり、今後はさらに拡大しそうな勢い。食品システムに詳しい豪州メルボルン大学のレイチェル・キャリー教授は「自然災害や供給チェーンの混乱に備え、都市は保険政策として都市農業能力を高めるべきだ」と指摘します。
一方、米国でも東部のシアトル市で、主に黒人と先住民族の間で都市農業が流行。失業者や生活困窮者にとっての自給自足手段として広がっています。
きっかけは、黒人差別抗議運動(ブラック・ライブズ・マター=BLM)を主導する社会活動家のマーカス・ヘンダーソン氏が、小さな野菜畑を作ったこと。同氏はBLM問題を巡り警察や機動隊と激しくぶつかり合う暴力的な日々を問題視し「殴り合いよりも、差別や失業で苦しむ黒人を助けるのが優先だ」と行動を起こしました。
同氏に賛同する黒人農家らが「本格的に都市住民のための農業を興そう」と集まり、「自分の食料を自分の手で作ろう」をスローガンに、人種差別やコロナ禍で失業した生活困窮者の参加を呼び掛けています。
2021年01月17日
次回はこちら
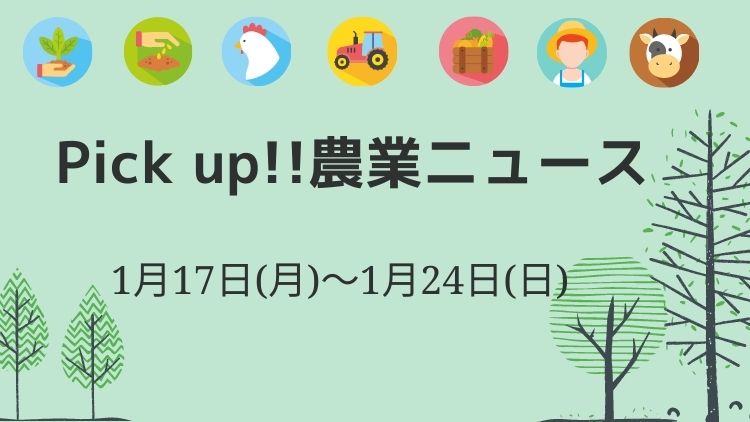
この記事が気に入ったら
フォローしてね!